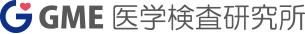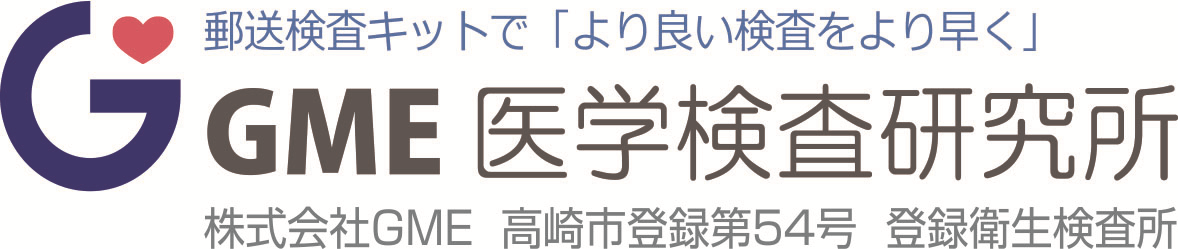さいきんせいちつしょう
細菌性腟症
さいきんせいちつしょう
細菌性腟症
細菌性腟症とは
細菌性腟症とは、女性の腟内の乳酸桿菌(ラクトバシラス属)の菌量の減少に伴い、腟内の正常な細菌集団のバランスが崩れ、様々な好気性菌(酸素があると増殖できる菌)や嫌気性菌(酸素があると増殖できない菌)が、腟内で異常に増殖している状態のことです。
腟炎の中で、カンジダ属、トリコモナス、淋菌などの特定の微生物が検出されないものを「非特異性腟炎」、または、「細菌性腟症(Bacterial Vaginosis:BV)」と呼びます。
腟内環境の変化で異常に増殖した細菌が上行し、子宮頸管を通過すると、子宮頸管炎や子宮内膜炎、さらに上行すると卵管炎や骨盤腹膜炎などを引き起こすので注意が必要です。
妊婦の細菌性腟症は、絨毛膜羊膜炎、産褥子宮内膜炎などと関係があり、特に、妊娠後期に細菌性腟症が起こると、早産による低出生体重児、新生児の肺炎・髄膜炎・菌血症などの感染症の原因になります。
腟炎の中で、カンジダ属、トリコモナス、淋菌などの特定の微生物が検出されないものを「非特異性腟炎」、または、「細菌性腟症(Bacterial Vaginosis:BV)」と呼びます。
腟内環境の変化で異常に増殖した細菌が上行し、子宮頸管を通過すると、子宮頸管炎や子宮内膜炎、さらに上行すると卵管炎や骨盤腹膜炎などを引き起こすので注意が必要です。
妊婦の細菌性腟症は、絨毛膜羊膜炎、産褥子宮内膜炎などと関係があり、特に、妊娠後期に細菌性腟症が起こると、早産による低出生体重児、新生児の肺炎・髄膜炎・菌血症などの感染症の原因になります。
原因
女性の腟は、デーデルライン乳酸桿菌の作用で粘液が酸性に保たれ、他の細菌の繁殖を防いでいます。しかし、種々の原因によりデーデルライン乳酸桿菌の菌量や活性が低下し、この自浄作用が低下すると、様々な菌が増殖しやすくなり、大腸菌、ブドウ球菌、連鎖球菌などの細菌が通常以上に増殖して、細菌性腟症となります。
主な原因

体調不良、過労、ストレス
体力・免疫力が低下すると、細菌性腟症になりやすくなります。
体力・免疫力が低下すると、細菌性腟症になりやすくなります。

性交渉のパートナーが複数いる・性交渉のパートナーが新しく変わる
不特定多数の人と性交渉をもつと、なりやすくなります。
不特定多数の人と性交渉をもつと、なりやすくなります。
症状と潜伏期間
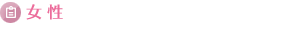
- おりものが灰色で、さらさらしている。
- おりものに悪臭(魚臭)がある。
外陰や腟のかゆみ、発赤を伴うこともありますが、それほど多くはありません。
萎縮性腟炎(老人性腟炎)とは
加齢につれて、エストロゲン分泌が低下すると、腟壁萎縮が起こり、性行為などにより腟損傷・腟炎が起こると、腟壁や子宮頸部などに、発赤・血性の小さい斑点が生じやすくなります。
これを萎縮性腟炎(老人性腟炎)と呼び、細菌性腟症とは区別されます。
加齢につれて、エストロゲン分泌が低下すると、腟壁萎縮が起こり、性行為などにより腟損傷・腟炎が起こると、腟壁や子宮頸部などに、発赤・血性の小さい斑点が生じやすくなります。
これを萎縮性腟炎(老人性腟炎)と呼び、細菌性腟症とは区別されます。
検査について
◎検査を受けられる機関
● 病院・医療機関(婦人科)

◎検査について
WHOの細菌性腟症の診断基準
以下の、4項目のうち3つ以上の項目が満たされた場合に、細菌性腟症と診断します。
以下の、4項目のうち3つ以上の項目が満たされた場合に、細菌性腟症と診断します。
① 腟分泌物の性状
腟分泌物の性状は薄く、均一である。
② アミン臭の有無
腟分泌物に、10%KOHを1滴加えた時に、アミン臭がある。
③ 腟分泌物のpH
腟分泌物のpHが4.5以上である。
④ 分泌物内の細胞
腟分泌物の生食標本で、顆粒状細胞質を有する「clue cells」が存在する。
予防
性的接触
細菌性腟症は、性的パートナーが多い女性がなりやすいと報告されています。
不特定多数の男性との性交渉を行わないよう心がけましょう。
不特定多数の男性との性交渉を行わないよう心がけましょう。
過度な腟洗浄は控える
習慣的に腟洗浄を行うと、腟内を正常に保つ働きをしている常在菌まで洗い流されてしまい、細菌集団のバランスを崩す原因となります。過度な腟洗浄は避けましょう。
治療法
細菌性腟症の治療には、局所療法と内服療法とがあり、現在は局所療法が主流です● 局所療法 (クロラムフェニコール腟錠・メトロニダゾール腟錠など)
治療効果を高めるため、治療初期には、滅菌蒸留水または生理食塩水で腟内を洗浄します。
服用期間 :
薬剤の種類により異なりますが、おおむね3~6日間投薬します。
● 内服療法 (メトロニダゾールの経口投与など)
服用期間 :
薬剤の種類により異なりますが、おおむね7日間程度服用します。
治癒判定 :
治療(局所・内服)後、腟内の状態を観察し、投薬・服用の効果を判定します。
不完全な治療を避けるため、必ず投薬・服用後の検査が必要になります。
不完全な治療を避けるため、必ず投薬・服用後の検査が必要になります。
検査サービスについてご不明な点がございましたらお問い合わせください
フリーダイヤル
0120-219-912
携帯電話からはこちら
受付時間10:00~19:00365日対応